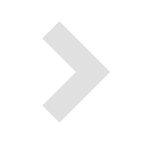はじめに
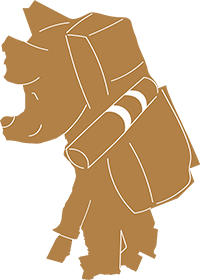
停留と移動
家の「外」に出るだけで、なんだか嬉しい気持ちになる。そんな感覚を味わうことになるとは、想像もしていなかった。しばらく、あまり家から出ることもなく、平板な画面ばかりを眺めて過ごすことが多かった。 2022年の春、ぼくたちは、通勤、通学のある毎日を過ごすようになった。もちろん、初めてのことではない。だが、ずっと疑いなく受け容れてきたはずの日常が、なんだかちがって見えてくるような、不思議な感覚をおぼえた。
こうした変化は、〈オンラインか対面か〉という対比によってとらえられることが多い。「3年ぶり」ということばが多用され、画面越しのコミュニケーションから解放されたことを喜ぶ。何気ない仕草や、間合いなど、身体が果たしていた役割をあらためて実感している。ぼくたちのコミュニケーションには、非言語的な手がかりは欠かすことができず、文字どおり立体的にお互いを理解することの価値を味わっている。
いうまでもなく、コミュニケーションは、いつか・どこかでおこなわれる。つまり、時間と空間が相まって、コミュニケーションの現場がつくられるのだ。そのために、ぼくたちは、約束をする。時間を調整したり、場所を探したりする。家にいるのか、出かけるのか。いつ出かけて、どのような経路を辿って目的の場所に向かえばいいのか。人とのかかわりを思案する。このプロジェクトは、〈オンラインか対面か〉のみならず、〈停留か移動か〉という観点から、これからの日常生活を考える試みである。
車窓を流れる風景
いま述べたように、COVID-19の影響下での暮らしのなかに、少しずつ(物理的な)移動の機会が増えてきた。長らく休んでいた身体をなじませつつ、あらためて通勤経路について考えてみた。ぼくの場合は、クルマで通勤することが多い(とくにこの2年は公共交通機関をなるべく避けるようにしている)。いうまでもなく、通勤のドライブで大切なのは、家とキャンパスとの間をできるだけ効率的に移動することだ。もちろん快適であることも求めたいが、景色を味わったり気まぐれに寄り道したりする余裕はない。むしろ、そうした誘惑に負けないように渋滞情報を確認し、時間に遅れないように家を出発する。
順調にいけば、1時間ほどのドライブでキャンパスに到着する。いつも同じルートなので、同じ風景が車窓を流れる。季節の変化には気づくが、家とキャンパスとの〈あいだ〉についてはほとんど実態的な理解がない。とりわけ大半は高速道路を走っているので、どちらかというと単調で個性を感じることのない風景を眺めている。くり返しているうちに、移動の〈あいだ〉は、たんに消費する時間として考えるようになる。
ぼくは、一人の通勤者として高速道路を行き来している。じつは多くの人の日常生活から、高速道路のようすは見えづらくなっている。そもそも高架であれば目は届かないし、防音壁に遮られていれば、クルマの往来は隠されてしまう。だから、高速道路は、点在するインターチェンジを結ぶ「線」として理解されることになる。高速道路を降りたら、こんどはキャンパスまでの「線」を辿るだけだ。
界隈への関心
ぼく自身の通勤経路は、家とキャンパスを結ぶひと筋の「線」なのであって、長きにわたって、この線上をなるべく早く行き来することがルーティンとなっている。途中で立ち寄るのは、コンビニとガソリンスタンドくらいだ。さらにいえば、ぼくたちが通うキャンパスは、木々に囲まれている。ちょうど高速道路のようすが見えないのと同じで、キャンパスは森に隠されているかのようだ。
クリネンバーグは、『集まる場所が必要だ』のなかで、キャンパスの成り立ちは、さまざまな理由で防御的になり、大学関係者と近隣に暮らす人びと(地域社会)との緊張関係を生む可能性があることを示唆している [1]。たしかに、ぼく自身は、森に守られた安全なキャンパスで日々を過ごしてきたが、界隈をあまり知らない。緊張関係ではないものの、地域社会とは切断されているように思える。学生たちも、キャンパスの近所に住んでいれば別だが、キャンパスと駅との〈あいだ〉にかんするイメージは希薄なのではないだろうか。
いわゆる「学生街」がキャンパスを取り囲んでいるわけではないので、学生たちは、もっぱら森の中に引きこもり(それなりに居心地がいいことはたしかだ)、〈あいだ〉を迂回して駅に向かう。これが、郊外型キャンパスの宿命なのだろうか。「地域に開かれたキャンパス」を標榜するとき、じつは、キャンパスの界隈にこそ目を向けることが、求められているはずだ。
親密で見知らぬ場所
キャンパスは、藤沢市遠藤(神奈川県)にある。ぼくたちは、キャンパスに親密さを感じながらも、じつは界隈をよく知らない。富田は、「親密性」と「匿名性」という観点から「インティメットストレンジャー(親密な見知らぬ他人)」という概念を導出し、メディア環境の理解を試みている。これを物理的な環境に転用して考えると、遠藤は「親密で見知らぬ場所」とも呼ぶべき存在だといえるだろう。慣れ親しんだキャンパスの「外」に踏み出せば、ぼくたちは、すぐさま名も無い存在に変わる。知っていてもよさそうなのに、ほとんど知らない間柄だ。
2022年度春学期は、キャンパスをとりまく遠藤地域を「となりのエンドーくん」と呼び、フィールドワークを実施することにした。これまでは、どこか(ランドマークとなる建物など)を中心に半径500メートルの円を描き、その中をくまなく歩き回るような悉皆調査の方法を何度か採用してきた。今回は、「遠藤」を対象地に設定した。「エンドーくん」の輪郭を描いただけで、キャンパスのすぐ南側は茅ヶ崎市に接していることに、いまさらながら気づく。知らないことは、たしかめよう。身体をつかって、「親密で見知らぬ場所」の理解を創造しよう。
学期をとおして、4つのグループが、それぞれの個性的な方法で、「エンドーくん」をとらえた。このサイトは、その成果をまとめたものである。「親密性」と「匿名性」をキーワードに、〈停留と移動〉のありようを読み解くことができるかもしれない。
[1] エリック・クリネンバーグ(2021)『集まる場所が必要だ:孤立を防ぎ、暮らしを守る「開かれた場」の社会学』英治出版
[2] 富田英典(2009)『インティメイト・ストレンジャー:「匿名性」と「親密性」をめぐる文化社会学的研究』関西大学出版部